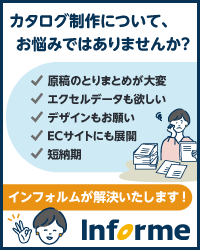行頭・行末のルールを考える
文章の区切りと行
印刷物では、文章をどのように組むかによって読みやすさ(可読性)や読むスピードが違ってきます。印刷物を読みやすく、誤読されないようにするには適切な組み方が必要なのです。
読みやすい文章を組むという点で、まず考えなければならないのは、文の区切り目です。文章を読んでいく場合、人は書かれている言葉の意味を理解しながら、論理の筋道をたどっていきます。文の区切りは意味の上でも区切りになる場合が多く、読んでいく上で重要な手がかりになるのです。
文の区切りの扱いは言語の構造によって異なります。英語など多くの欧米系言語はアルファベットという表音文字を使い、単語と単語間隔(スペース)の組み合わせによって語句を区切り、さらにピリオドやカンマなどで文章を区切りますが、漢字という表意(表語)文字を使う中国語のような言語では、単語ごとにスペースなどの視覚的な区切りを入れる必要はありません(句読点は古くから使われている)。
表意(表語)文字である漢字だけで文が構成されている中国語に対して、ひらがな・カタカナという表音文字も併用されている日本語の場合、単語を分ける区切りが必要になることがあります。漢字が使われていない幼児向けの本などで、単語や語句ごとにスペースを入れる「分かち書き」で組まれているものを見たことがあるでしょう。これは、ひらがなだけの文章では単語の区切りがないと理解するのが難しいということを示しています。
一方、一般の日本語の本は、漢字にひらがな・カタカナなどの表音文字が適宜に組み合わされることで、自然と単語の区切れを把握しやすくなっており、句読点など最小限の区切りで十分分かりやすい文章になります。
要するに、欧文組版では、単語(およびスペース)を見やすいように区分けすることが意味を理解する上できわめて重要なのに対して、日本語組版だと、せいぜい句読点やカギ括弧などを入れる程度、場合によっては途中に切れ目がない文でも理解できる仕組みになっているわけです。
そもそも、日本の昔の文章には読点や括弧ばかりか句点すらなく、文がどこで終わり、どこから始まるかも見た目だけでは判断できないことが珍しくありませんでした。それでも特に混乱もなく使われていたということは、日本語という言語が、見た目(組版上)の区切りをそれほど必要としないということなのかもしれません(もちろん、あったほうが分かりやすいのは当然です)。
ところで、長い文章には「行」という要素があります。文章を読む場合、人間の目は行の始まりから終わりに向かって動き、さらに次の行の始めに飛ぶ、というように視線を動かします。行は長い文章を限られたエリアに効率的に組むための組版上の区切りであり、意味や論理構造と必ずしも一致しません(もちろん詩などは別です)が、いずれにしても何らかの区切りを読者に印象づけるものであることに変わりはありません。
ハイフネーションのルール
単語とスペースによって文章を構成する欧文では、スペースが区切りとなるので、行の終わりすなわち改行もスペースの位置で行うのが普通です。
単語の長さがバラバラで、文字の幅もそれぞれ異なる欧文の場合、スペースの位置が常に一定になるというわけにはいきません。当然ながら、そのままでは改行の位置もその都度違ってくることになります。
日本語組版の場合は複数の行がある文章の場合は行末を揃えるのが一般的ですが、欧文組版の場合、適当な位置で改行したまま行の長さを無理に揃えない組み方もよく見られます。こういった組み方を「ラグ組み」と言い、左揃え、中央揃え、右揃えといった種類があります。
ラグ組みの場合は、改行する位置だけが問題であり、文字間隔やスペースの幅などは常に一定です。それに対し、行末を揃えて行の長さを一定にする組み方を「ジャスティフィケーション」(ジャスティファイ)と言います。
ジャスティフィケーションの場合、本来であれば揃わない改行位置を揃えるために主にスペースの幅を調整することになります。ただし、スペースだけで揃えようとすると見苦しくなる場合、単語中の文字間隔を調整することもあります。
これで行末が揃えばいいのですが、行末に長い単語がきた場合などで、調整すると単語間隔や文字間隔が広くなりすぎることもあります。そういった際に行われるのがハイフネーション処理です。
ハイフネーション処理は、行末にかかる単語を途中で分割し、前の部分にハイフンを加えて行末に収め、後の部分は次の行に入れるというものですが、そのポイントは、どこで単語を分割するかという点です。
英語やフランス語などは、単語をシラブル(音節)という単位で分けることができます。シラブルは、母音を中心にしたひとまとまりのグループです。各シラブルに母音はひとつだけ(多重母音はひとつと数える)ですが、子音はいくつあってもかまいません。たとえば、「justification」という英単語は「jus-ti-fi-ca-tion」に分けられるので5つのシラブル、「straight」という単語には母音がひとつしかないのでひとつのシラブルでできている単語ということになります。シラブルは単語の音の面でもっとも基本となる単位です。
ハイフネーション処理は、必ずシラブルの間で分割しなければなりません。つまり、ひとつのシラブルでできている単語にはハイフネーション処理ができないわけです。なお、ハイフネーションで1文字になるような分割は避けるといったルールもあります。
ちなみに、ハイフンの入る位置は言語によって異なります。最近はレイアウトソフトにシラブルデータを含む辞書が搭載されるようになりましたが、同じ綴りでもどの辞書を使うかによって処理の結果も変わる可能性があるので注意が必要です。
なお、ハイフネーション処理は、あまり続けると見た目が良くなく、可読性にも影響が出ます。そのため3行以上は続けないようにするのが一般的です。
禁則処理の考え方
大小さまざまな単語とスペースの組み合わせが基本になる欧文組版では、行末におけるハイフネーション処理は必然的と言えるでしょう。
一方、日本語の場合、欧文と違って単語の途中で改行があるのは問題になりません。文章の構造上、欧文の単語・シラブルにあたるのは日本語では文字であり、文字自体が分割されるわけではないのでハイフネーション処理は必要ないのです。ただし、句読点や括弧といった文章上の区切りの記号が行の区切りと矛盾するのは読み手に混乱をもたらすので避けなければなりません。その際、文章中にスペースがないことが、かえって処理を複雑にする要因にもなります。
行の終わりがちょうど意味の区切りであればいいのですが、場合によっては行の終わりと意味の区切りの関係を調整する必要が出てきます。たとえば、句読点が行の頭にきた場合です。句読点は意味の区切りですが、それが行の頭にくることで、組版上の区切りに続いて意味の区切りがくることになります。読者としては、視覚的な区切りが二つあるように思われ、混乱してしまいます。
このように、組版上の区切りと行頭・行末の関係に問題がある場合、それを回避するためのルールが「禁則」です。
終わりを意味する区切りが行頭に来てはならない、始まりを意味する区切りは行末に来てはならないというのが基本的な禁則ルールです。句読点や閉じ括弧類は文や語句の終わりを意味する区切りの記号であり、行頭にくるべきではありません。また、開き括弧類は語句の始まりを意味するので行末にきてはなりません。
これらは、文法上の区切りと行頭・行末の関係による禁則ですが、そのほかに発音に関係する問題による禁則もあります。
たとえば、「々」「ゝ」「〃」など、前の字を受けて繰り返す記号や長音記号など、単独では読むことができない記号は、前の字と行が別れると分かりにくくなります。そのため、行頭にはこないようにする(行頭禁則)というのが一般的です。
さらに、小さな「っ」(促音)や「ゃ」「ゅ」「ょ」(拗音)も行頭禁則に含めることがあります。これらも、単独では発音できず、前の字を受けて(一体となって)音を形成します。もっとも、このような“発音を考慮すると区切れない文字”まで禁則に含めると、改行位置での制約が強くなりすぎるからか、あるいは歴史的仮名遣いでは拗促音は小書きにならず発音に配慮する必要がなかった過去の組版の影響か、禁則にしないケースも少なくありません。
禁則ルールは、読みやすさを追求した結果生まれてきたルールであり、確固とした基準があるわけではありません。出版社や出版物によって異なる禁則ルールがあり得るので、組版をする際は求められている禁則ルールをよく確認することも大切です。
(田村 2007.6.18初出)
(田村 2024.1.9更新)