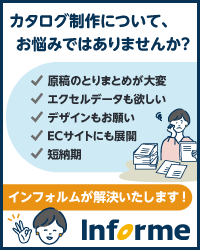本文文字詰めを考える
なぜ文字を詰めるのか
DTPでは、文字は専門のフォントデザイナーが作ります。彼らは、可読性が高く、また、想定される使用目的に適ったフォントを作るために、一つ一つの文字の大きさ、次の文字との流れを考えながら作業していきます。当然、出来上がったフォントを使えば、そのまま流し込むだけでデザイナーが考えた通りのきれいな文字組みが出来上がるはずです。
ところが、実際の組版作業では、テキストを流し込んだだけでなく、文字の間隔を詰める文字詰めという処理がよく行われます。
もちろん、見出しなど文字サイズが大きな場合は、同じフォントでも小さな文字の場合よりどうしても文字の間隔が開きすぎて見えるため、間を詰める必要がありますし、本文でも約物の処理などによって、どうしても文字間を詰めなければならない部分が出てくることもあります。ところが、そういった場合でない本文部分で文字間を一括に詰める指定が入るケースが少なからずあるのです。
本来であればそのままでもいいはずの文字間隔をどうしてわざわざ手間をかけて詰めるのでしょうか。
文字を詰める理由として「いんふぉるむマガジン」読者のデザイナー大熊肇(図南)氏より興味深い話をお聞きしました。それによると、「初期の手動写植機はレンズの性能が悪く、カメラで言う「俵型のゆがみ」があり、外になるほどゆがみが強く出ること、また、文字盤の周りが固められておらず2枚のガラスの周りをテープで止めているというもので精度が悪かったことから、字面を大きくすると詰まりすぎ、空きすぎが目立つものだった」そうです。そのため、文字を均等詰めする必要があったということです。
もちろん、現代のデジタルフォントにこういった問題はなく、その解決のために字面が小さく作られているということもありません。字面の小さなフォントは、均等詰めするためでなく、あくまでデザイン的に文字のアキを広めにするために作られているのです(例外として、凸版印刷が開発した「こぶりな」は、均等詰めを前提に字面を小さくしてある)。
要するに、初期の手動写植機の不具合を回避するTipsが、どういうわけかDTP時代にまで受け継がれてしまったというわけです。伝統文化には深い敬意を覚える私ですが、こんな伝統はありがたくありません。
文字を詰める理由としては、他に、情報を詰め込むため文字数を増やす必要があるというものもあるでしょう。
たとえば、昭和十年代、戦争が泥沼化した日本では次第に物資が窮乏するようになり、中でも紙の不足は深刻でした。大サイズの紙を使って毎日発行していた新聞も例外ではなく、ページ数の制限に追い込まれます。そういった状況で、できるだけ多くのニュースを掲載しようとすると文字組みを工夫しなければなりません。そこで考え出されたのが文字を扁平にするという方法です。
文字の縦よりも横幅を長くすることで、文字の大きさをできるだけ維持しながら文字を詰め込むことが可能になります。太平洋戦争開戦の昭和十六年から新聞各社でこぞって採用されたこの扁平書体は、戦後になり、紙不足が解消しても新聞独特の書体として今に引き継がれています。
新聞以外の媒体では、扁平書体を使うことはほとんどありません。しかし、文字間隔を詰めることで、限られた紙面に文字をできる限り多く掲載するというやり方は、新聞のこの扁平書体と一脈通ずるところがあるように思います。
文字を詰めるもう一つの理由としては、見た目のバランスを求めるというものがあります。1970年代になると、雑誌の分野でも写植が一般的になるとともに写真をメインにおしたてた雑誌が出てきます。それに伴って文章がブロック単位のキャプションとしてパーツ化され、写真と同じオブジェクトとして扱う手法が使われるようになってきます。
この場合、文字は読ませるものというより見た目が重視されるひとつのデザイン要素、パーツのひとつとして扱われます。ただし、英語などと違い、漢字とかなが混じって表記される日本語では、均質なブロックとはならないという問題があります。画数の多い漢字が偏って配置されることで紙の白地と文字の黒の割合が一定にならず、濃度のムラが生じるのです。そこで、文字を詰めることでブロック全体を均質なグレーに近づけるという考え方もでてきました。
この考え方では、漢字よりも文字幅の小さいかなを詰め、また、同じかなでも文字幅の小さな文字は余計に詰めるといった微調整(プロポーショナル詰め)を行うことで、より均質なグレーができることになります。
この考え方は、日本語の読みやすさ、可読性ということをあまり考慮しておらず、あくまでグラフィカルに処理することだけを追求したものと言えます。書籍など文章を読ませる印刷物に使うのは避けたほうがいいでしょう。書家でもある大熊肇氏は自らのWebサイト上で「縦書きでは筆脈がつながるように組まれなければならず、プロポーショナル詰めはするべきでない」と具体例を挙げて指摘しています。
実際、文字をむやみに詰めると可読性が悪くなるのは確かです。とはいえ、DTPのオペレーターからすれば、クライアントから要求されればやむを得ずそれに応えなければならないというのも現実なのです。
文字詰めの種類
文字間隔を詰めるやり方は、均等詰めとプロポーショナル詰めの二つに大きく分けることができます。均等詰めとは、全ての文字間隔を一律に一定量詰めていくことであり、「1歯詰め」などの指定がよく使われます。
均等詰めは、一律に一定量の詰めを行うため、一行に入る文字数が計算できるというメリットがありますが、書体や文字サイズ、詰める量によっては文字がくっついてしまったりするなど問題が生じる可能性があります。
プロポーショナル詰めというのは、文字ごとに異なる文字幅にあわせて文字間隔を詰めていくというものです。欧文組版ではアルファベットの文字ごとに異なる文字幅にあわせて文字間隔が定められるというのが一般的ですが、日本語組版でもこの処理を行うわけです。
そのほか、日本語テキストのうち、かなだけを詰める「かな詰め」も一般的に行われています。
ここで、InDesign(インデザイン)を例に、DTPソフトでの文字詰め設定を見ていきましょう。InDesignで均等詰めをする場合は、文字パレットやスタイル設定の「字送り」(他ソフトのトラッキングにあたる)またはフレームグリッド設定の「字間」で数値を指定するだけです。なお、字送りとフレームグリッドの「字間」は厳密に言うと違いがあります。「字送り」は和文も欧文も同じように詰めますが、フレームグリッドの「字間」は和文だけを詰めるため、和欧混在の文章にはフレームグリッドの「字間」を使う方がいいでしょう。
プロポーショナル詰めは、フォントごとに詰める値が違うので、フォントの文字幅情報を取得しないと自動で処理することはできません。OpenTypeフォントであれば、OpenType機能の「プロポーショナルメトリクス」を使えば自動で詰められますが、TrueTypeフォントなどでも、文字パレットの「文字ツメ」機能を使うと、文字幅に合わせて自動的に詰めることが可能です。
プロポーショナル詰めは、文字ごとに最適な間隔を指定するために文字がくっつくといった問題はありませんが、書体によって詰まる量が大きく変わり、どの程度詰めるべきか判断しにくい、文字数計算が困難といったデメリットがあります。先ほど書いたように、可読性という点でも問題があるので、使う際は、デメリットについても十分考慮する必要があります。
かな詰めは、漢字に比べて一般的に文字幅の小さいかなだけを詰めるため、文字がつき過ぎる弊害が少なく、また漢字を詰めないので可読性もある程度保つことができるのがメリットです。
InDesignでかなの均等詰めをするには、文字組みアキ量設定でかなだけを詰めるように設定します。また、かなをプロポーショナルで詰めたい場合、OpenTypeフォントであれば、検索・置換でかなを選択(文字種変換)し、OpenType機能の「プロポーショナルメトリクス」を指定すれば、かなだけをプロポーショナル詰めすることができます。
(田村 2007.3.19初出)
(田村 2016.5.25更新)