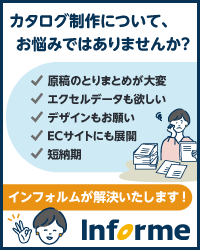ルビ
漢字を読むための仕組み
日本語組版の特徴のひとつに「ルビ」の存在があります。ルビとは印刷物で漢字などの文字の隣りに入れてその文字の読みかたを表す小さな文字のことで、「振りがな」あるいは「読みがな」とも呼ばれます。
ルビが使われるようになったそもそもの根源は、日本語における文章表記の特殊さにあります。ご存じのように日本で文章が書かれるようになったのは中国から漢字を移入してからのことです(それ以前に独自の古代文字があったという説もあるが学会は否定的)。
私たちの祖先は外国語の文字である漢字を使い、最初は外国語である漢文を書いていましたが、それにとどまらず、漢字の音を利用して日本語を表す万葉仮名を考え出し、続いて日本語独自の表音文字であるひらがな・カタカナを作り上げました。さらに、漢字そのものに日本語の読みを当てる訓読みも編み出され、これらによって、漢文をそのまま日本語の文章として読み下す訓読(くんどく)や、漢字とかなを混在させる漢字かな交じり文という表記が可能になったわけです。
このように漢字を使った多彩な表記が使われるようになってくると、漢字をどう読むかということが重要になってきました。
元々、漢字には中国から伝わった読み方(呉音・漢音)がありました。漢文しかなかったころは、中国語を理解できる者しか漢字を使わなかったわけで、漢字の読み方はそれほど問題にならなかったでしょう。知っていて当然だからです。
ところが、訓読や漢字かな交じり文が一般的になり、中国語を知らない人間が漢字を扱うようになってくると、知らない漢字があった場合でも何とか読めるように発音を示す必要が出てきます。
漢文を日常的に扱う人たちの間でも、原文(白文)を訓読するために返り点や送り仮名のほか、読み仮名を原文に付け加えるということが早くから行われていました。昔も原文を一目見ただけですらすら読める人ばかりではなかったということです。同じように、漢文の書き下し文や漢字かな交じり文であっても、読み仮名を漢字に付けることでその漢字を知らない人間でも読むことが可能になるわけです。
江戸時代になって庶民の間でも木版印刷が普及してくると、漢字に読み仮名を振った印刷物が一般的になります。そして明治になり、活版印刷が登場すると、活字を使ってそれまでと同じように振り仮名を振った印刷物が普及していったのです。
手彫りの木版印刷と違い、活版印刷の場合は振り仮名に本文用の活字よりも小さな活字(一般的には本文用文字の半分のサイズ)が必要になります。当時本文用の活字として一般的に使われていた5号(10.5ポイント)活字に合わせるルビには7号活字(5.5ポイント)が使われましたが、5.5ポイント活字をイギリスで「ruby」と呼んでおり、これが輸入されて使われたことから印刷業界では振り仮名のことを「ルビ」と呼ぶようになったようです。
モノルビとグループルビ
さて、印刷物でルビを振る場合、まず考えなければならないのは親文字(ルビを振る元の漢字)にルビをどう割り振っていくかということです。ルビの振り方には大きく分けてモノルビとグループルビがあります。
モノルビは、対応する親文字1字ごとにルビを振っていくというものです。たとえば「茨城」という文字にルビを振る場合、「茨」に「いばら」、「城」に「き」と振るのがモノルビです。
一方、グループルビは複数の親文字全体にまとめて振るルビのことです。「茨城」であれば「茨」から「城」までに均等にルビが振られるため、「茨」の上に「いば」、「城」の上に「らき」と振られることになります。
モノルビは、文字ごとに読みを振るため、教科書や学習参考書などのように各文字それぞれの読みを正確に伝えたい場合に便利です。ただし、親文字に3字以上の長いルビが付く場合は、モノルビよりもグループルビのほうが柔軟に対応できることがあります。「茨城」の例で言えば、「茨」に「いばら」というルビを振ると親文字よりも長くなり、親文字の間隔をあけるとかルビを他の字にかけるといった処理をしなければなりませんが、グループルビであれば「茨城」の範囲に収まります。
また、複数の文字列を1文字単位に分けることが出来ない場合もあります。たとえば「五月雨」(さみだれ)、「明後日」(あさって)のように熟字単位で訓読みを当てる「熟字訓」はモノルビを振ることが出来ません。
さらに、意味の違う文字で音だけを流用する「当て字」や、読み仮名に外来語を使う場合も、グループルビを使うのが一般的です。
熟語ルビ
日本工業規格、すなわち組版処理の製品に対する規範という形で日本語の組版ルールを規定する「JIS X 4051」が2004年に改訂され、そこで新たに「熟語ルビ」という概念が導入されました。
これまで、DTPソフトをはじめとして日本語文書を扱うソフトにはモノルビとグループルビの機能が搭載されてきました。ところが、実際に組版処理を行う上で、この2つだけでは十分ではないケースが少なからずありました。
たとえば、ルビの文字数が少なければモノルビで問題ありませんが、熟語にかかるルビで部分的に親文字からはみ出すような場合、グループルビのほうが収めやすいこともあります。しかし、グループルビにすると、熟語の途中で改行が入る場合に処理できないことになってしまいます。
そこでJIS X 4051:2004では、モノルビとグループルビの特徴を組み合わせた「熟語ルビ」という新しい仕組みを導入したのです。熟語ルビの場合、熟語のどの親文字からもルビがはみ出さない時はモノルビと同じように組み、ルビがはみ出す部分はグループルビの組み方に変わり、さらに熟語の途中に改行が入るとモノルビのように分離するという動きになります。
熟語ルビを使えばルビの扱いがかなりラクになることは間違いないでしょう。今のところまだ熟語ルビを使う製品はないと思いますが、JIS規格は製品の規範ともなるものであり、組版処理を行うソフトはこの新たな規格に則った製品開発が求められます(強制するものではない)。熟語ルビもいずれDTPソフトやワープロソフトで一般的になってくるでしょう。
(田村 2007.8.20初出)
(田村 2016.5.25更新)