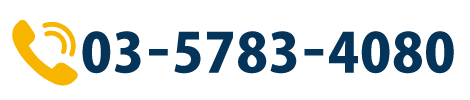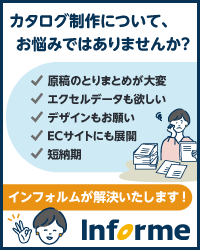文字列を揃える機能
スペースで揃えることの問題
箇条書きやリストが多用される印刷物では、各行の文字列を、行の頭でなく途中の位置で揃えるということが少なくありません。そういった場合に、全角や半角スペースを使って文字の始まりの位置を揃えている原稿テキストをよく見かけます。
確かに、単機能のテキストエディタなどで文字列を行の任意の位置に揃えたいのであればスペースを使うのも分からなくもないのですが、もちろんこれはDTPの原稿テキストとしては不適切なデータです。
スペースで位置を調整した場合、文字列が複数の行にまたがる場合の処理がDTPソフトではまず問題になります。段落1行目と同じ位置で2行目以降を揃えたい場合、2行目以降の行頭にそれぞれスペースを入れていけば始まりの位置は揃えられますが、もし1行目に修正が入り、文字数が増減すると2行目以降の開始位置が全て変わってしまい、揃わなくなってしまいます。
また、複数行の場合、行末を揃えるにはジャスティファイ処理が必要になってきます(禁則処理を行うため)が、そうなるとスペースの伸縮が起き、結果として行の開始位置が揃わなくなるということもあり得ます。
そもそも、スペースだと微妙な調整ができず、書体によっても幅が変化するなど、厳密に揃えることができません。
結局のところ、スペースを使って文字の位置を合わせるという方法は、文章が必ず1行に納まる箇条書きなど、複数行にまたがらない1行だけの段落が続くケースであれば使えないこともないものの、やむを得ない場合を除いて避けるべきでしょう。
タブとインデント
設定された位置まで文字の開始位置を飛ばすタブも、文字列を揃える場合によく使われます。タブ機能は、テキストデータを編集するアプリケーションのほとんどで使うことができるポピュラーな機能であり、プレーン・テキストでも他の文字と同じように保存されるのもメリットです。
また、スペースと違い、アプリケーションの設定によって正確な位置に文字を揃えることができるというのも、大きなアドバンテージでしょう。たとえば、InDesignであれば、千分の1ミリ単位の指定が可能です。書体やジャスティファイによって位置が変わるということもありません。
ただし、スペースの場合と同様、複数行にまたがるような長い文章だと、文字揃えにタブは使えません。たとえば、段落の頭にタブを入れた場合、そのままだと1行目だけタブが効いた状態で2行目以降は文字が行頭にきます。そこで2行目以降の改行位置でタブを入れて揃えると、1行目の文字が増減した際に文字組みがメチャクチャになってしまいます。
手軽に使える機能であり、スペースのように敬遠するべきものではありませんが、それでも使う場所には注意が必要です。
複数の行を同じ位置から開始する場合、DTPソフトやワープロソフトで一般に使われるのはインデント機能です。
インデントは行が始まる位置を下げるという機能で、DTPソフトでは段落全体の行の開始位置を設定することができます。段落が続く間はずっとこの開始位置が有効になっています。そのため、タブやスペースで調整することなく、指定通りの位置で文字を揃えることができるわけです。
1行目インデント
各行の文字列の開始位置を揃える場合、全ての行の開始位置を揃えたければ全体に左/上インデントを指定するだけでいいのですが、段落の最初の行だけ字下げする場合や、最初の行だけ行頭にして2行目以降を字下げするといった組版指定(いわゆる「問答」)もよくあります。そういった場合には、タブや「1行目インデント」を使うことになります。
段落1行目だけ字下げする場合、「スペースを入れる」「タブを使う」「1行目インデントを設定する」という3通りの方法があります。
スペースは1文字分下げる場合によく使われます。全角スペースを入れるだけなので、原稿テキスト作成時に入れられるというのが最大のメリットですが、ジャスティファイによって微妙に位置が変化する可能性があるというデメリットもあります。
タブは欧文ではDTP以前から採用されてきた方法です。テキストデータで段落頭にタブを入れておけば、タブの設定に合わせて字下げが行われます。
1行目インデントは、文字通り段落の1行目だけに適用されるインデントを指定するというものです。タブと違い、テキストデータには何も加えず、設定で字下げを行います。
InDesignの1行目インデントは、通常のインデントと組み合わせることで、複雑な処理も可能です。たとえば、タブは設定された絶対値に従って字下げが行われますが、1行目インデントは通常のインデントに対する相対的な位置を指定します。ある段落に10mmのインデントが指定されていたとして、1行目インデントを5mmに指定すると、1行目は15mm下げた位置から始まります。インデントを20mmにすれば1行目の開始位置は自動的に25mmとなるわけです。
この仕組みを利用すれば、1行目だけ突き出したインデント(問答)を簡単に作ることができます。適切なインデントを指定し、突き出す幅を1行目インデントにマイナスの数値で指定するだけです。ちなみに、1行目のテキストフレームからのインデント幅は「通常の左/上インデントの数値-1行目インデントの数値」ですが、テキストフレームからはみ出すことはないため、左/上インデントより1行目インデントの絶対値を大きくすることはできません。
InDesignの1行目インデントは、1つの段落に2種類のインデントを適用することができる便利な機能ですが、名前の通り1行目だけしか適用できません。段落頭の複数行だけ別のインデントを適用したい、といった場合には対応できないわけです。
なお、InDesignには、左/上、一行目、右/下という各インデントのほかに、段落の最終行の行末までの空きをコントロールする「最終行右/下インデント」という機能もあります。これは最終行の行末までの空きの最大値を指定し、この値を超えると次行に文字を送るというものです。
ここまでインデント
1行目インデントや通常のインデントを使う場合はきちんと数値を指定する必要がありますが、InDesignにはそれとは別に「ここまでインデント」という特殊文字が用意されています。
特定の文字間に「ここまでインデント」文字(制御文字であり実体はない)を挿入すると、次の行からその位置でインデントが行われるという処理が可能です。
数値は一切指定する必要がなく、しかも1行目だけでなくどの行でもインデント文字を挿入した次の行からインデントされるなど、使い勝手が良いため、比較的新しい機能ながら活用している人も少なくないでしょう。
ただし、この機能はあくまでインデント文字が挿入された位置を基準にしているため、修正などで位置がずれたときは、次行以降のインデント位置も変わってしまうことになります。
また、設定やバージョンの違いなどによっては思ったような結果にならないこともあり、十分な注意が必要です。
(田村 2009.11.24初出)
(田村 2025.3.24更新)