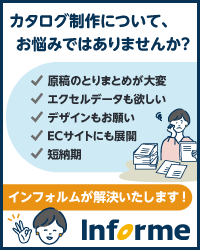色分解の基礎
画像の色分解
最近はデジタルカメラの普及で、写真がはじめからデジタルデータになっていることが多くなりました。デジタルカメラのデータはRGBカラースペースで記録されているため、印刷に使う場合はCMYKに変換(色分解)しなければなりません。
写真がフィルムカメラで撮影されていた時代、色分解は、撮影されたフィルムからデジタルデータを作るスキャニング工程で行われるものでした。専門の製版オペレーターが高性能なドラムスキャナを使ってスキャニングしていたため、制作オペレーターのほうはCMYK分解についての知識も必要なく、ほとんど製版にお任せということも珍しくありませんでした。
ところが、デジタルカメラの普及によってスキャニングのニーズが減ってくると、色分解を誰がいつ行うかというのが問題になってきました。最初からデジタルデータになっているデジタルカメラ画像の場合、色の専門家であるスキャナ・オペレーターの出る幕がありません。
最近では、制作工程では適宜色補正したRGB画像で運用し、最終出力時にRIPなどでCMYKに変換して出力するワークフローも見られますが、こういったやり方はカラーマネジメント環境がきちんと整備されていて、ワークフロー全体で統一した色管理が実現できていることが前提になります。
結局のところ、カメラマンや制作オペレーターがやむを得ずPhotoshopを使って慣れない色分解作業を行うというケースも少なくないようです。ただし、いくらPhotoshopが高機能でも、使いこなすのは人間である以上、色分解についてある程度の知識は必要になってきます。
Photoshopの色分解
1990年の発売以来30年以上の歴史を誇るPhotoshopですが、すでに初期のころから高度な色分解の機能が備わっていました。ただし、バージョン5を境に、その機能は大きく変化しています。
Photoshop 4までの色分解は、ユーザーがRGBとCMYKの設定を個別に行い、「イメージ」→「モード」→「CMYK」を実行すると、各設定を元に変換が行われるというやり方でした。特にCMYKの設定には印刷の知識も求められ、色の素人が簡単に使えるというものではありませんでした。
Photoshop 5からカラーマネジメントの考え方が導入され、現在ではRGBとCMYKのプロファイルを指定するだけで色分解をコントロールできるようになっています。画像のカラーモードをRGBからCMYKに切り替えると、カラー設定で指定されているRGB、CMYKそれぞれのプロファイルに基づき、RGBからCMYKへのカラースペースの変換が行われます。
最新バージョンにはJapanColorやJMPAカラー(雑誌広告基準カラー)に準拠したCMYKプロファイルが複数用意されています。これらのプロファイルを指定すれば、印刷がとんでもない色になってしまう危険はかなり減るはずです。
とはいえ、これらのプロファイルはあくまでも標準的な色を目指すものであり、場合によってはユーザー個々が設定をしなければならないこともあり得ます。そのためには、ある程度色分解について理解しておくことも大切でしょう。
CMYK設定
最新バージョンのPhotoshopでも、以前の色分解の設定は残されています。「カラー設定」でCMYKの作業用スペースに「カスタムCMYK」を選ぶと、従来のCMYK設定画面が現われます。ここにある項目は全て印刷の色を決める重要なものばかりです。
具体的に見ていきましょう。CMYKの設定は、「印刷インキ設定」と「色分解オプション」の2つに大きく分けられます。
印刷インキ設定には、印刷インキのベタ濃度(および二次色・三次色)の色を数値で指定する「インキの色特性」と、印刷インキのドットゲインを指定する「ドットゲイン」があります。この2つの項目は印刷の色を左右する大きな要素ですが、いずれもインキや印刷機の性質や状態、紙質などによって変わってきますし、印刷オペレーターが印刷物の色をどのようにしたいか、ということにも左右されます。それだけに、制作オペレーターとしては印刷サイドから情報を提供してもらわないことには指定のしようがない部分とも言えます。
次に、色分解オプションの欄を見ると、色分解の種類(GCRおよびUCR)、墨版生成、黒インキの制限、インキの総使用量、UCAといった項目が並んでいます。
色分解でまず問題となるのは、墨版をどう考えるかということです。本来、色の三原色はシアン、マゼンタ、イエローであり、ブラックはその掛け合わせで生成される色であって三原色ではありません。つまり、ブラックがなくてもフルカラーは可能なわけです。ただし、グレーの安定性や黒ベタの再現性、インク使用量の効率化などを考えると、墨版は必要です。
RGBからCMYKへの変換は、CMYKのうち、ブラックをどのように生成するかが重要なポイントになります。
RGBからCMYKへの変換は、Kを除くRGBからCMYへの変換がベースになります。色の再現できる領域は多少違いますが、3色の要素を組み合わせることですべての色を表現するという根本の原理は同じであり、グレーや黒はCMYを掛け合わせることで再現が可能です。ということは、CMYの掛け合わせによってできたグレーの成分をCMYとは別のK版に置き換えることもできるはずです。
「GCR」「UCR」や「墨版生成」は、CMYをどのように墨版に置き換えるかを指定するものです。簡単に言うと、GCR(Gray Component Replacement)はCMYの掛け合わせによる薄いグレー成分の段階から徐々に墨版に置き換えるもの、UCR(Under Color Removal)はグレー成分がある濃度を越えると越えた分が墨版として入っていくものとなります。
また、墨版生成は、GCR時にどれくらい墨版に置き換えるかをコントロールするための設定です。たとえば墨版生成を「最大」にすると、CMYの掛け合わせグレー成分を最大限墨版に置き換えますし、「なし」だと逆に墨版を一切使わず、CMYの掛け合わせだけで黒を表現することになります。
たとえば、パソコンのモニターなどの画面キャプチャ画像をCMYKに変換する場合、普通に色分解すると画面やダイアログなどの黒の文字が4色に分解されてしまい、版ズレで文字がにじんで見えるなど品質に問題が生じかねません。色分解時に墨版生成を最大にしておけば、黒文字はK版だけのデータになり、トラブルを防ぐことができます。墨版最大での色分解はともすれば表現に乏しいくすんだ画像になりがちですが、画面キャプチャであれば問題ないでしょう。
そのほか、二色印刷において色の掛け合わせで印刷する画像データは、墨版生成をなしにしてRGBからCMYへの変換を行い、C版とM版をベースの版として処理するというやり方が有効です。
なお、画像を色分解する際、注意しなければならないのは、オフセット印刷ではインクの総使用量に限界があるという点です。CMYKと一言で言いますが、実際にCMYKを全て100%で掛け合わせて印刷するのは困難です。
フルカラーのオフセット印刷には、4色のインクを一度に刷れる多色印刷機を使うのが普通ですが、その場合、インクが乾く前に別の色のインクを重ね刷りすることになり、後のインクが完全には乗らない「トラッピング」という現象が起きます(毛抜き合わせのトラッピング処理とは別物)。また、インクの量が多いとインクが剥がれるなどの印刷不良にもつながります。
こういった事態を避けるためには、インクの合計使用量をセーブすることが必要なのです。通常、インクの総使用量の上限は300%前後(日本では一般に高めなことが多い)ですが、印刷機や紙などの条件によって変わってくるので、印刷現場に確認しなければ決められません。
以上見てきたように、印刷の状況を正確に把握していなければきちんとした色分解は本来できません。だからこそかえってプロファイルを使った簡便な色分解が使われるようになってきたと言えるのかもしれません。Adobeが提供するCMYKプロファイルがPhotoshopなど同社製品でスタンダード的に使われるようになったことで、結果として日本の印刷物の色の標準化が進んだという面も否定できないでしょう。
ただ、標準的な色分解であれば問題はないかもしれませんが、上記に述べたように画面キャプチャや二色掛け合わせの分解など、ケースによってはユーザーによる分解設定が必要になることもあります。プロファイルの選択やカラーマネジメント製品の扱いなどを正しく理解するためにも、ユーザーにもある程度の知識が求められているのではないでしょうか。
(田村 2006.9.11初出)
(田村 2023.11.6更新)