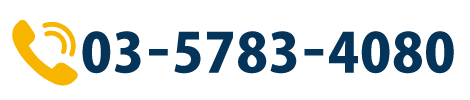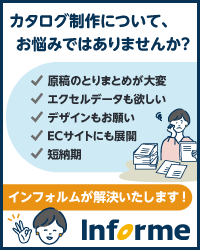ベタ濃度とドットゲイン
印刷物の色を決定する要素
DTPソフトを使ってデータを作っている時、私たちは、モニタに表示されている色が印刷でも同じように再現されると思って作業しています。しかし、実際に印刷で同じ色が再現されるかどうかは分かりません。
一般的なオフセット印刷の場合、DTP作業で作られたデータは、CTPという出力機で出力されて印刷用の原版となり、さらにオフセット印刷機で印刷物になります。この場合、データが違えばもちろん色も違ってきますが、仮にデータや版が同じでも印刷物の色が同じになるとは限りません。印刷機やインク、紙など、さまざまな要因によって、印刷物の色は変わってくるのです。
インクが違えば色が違うというのは理屈としても理解しやすいでしょうが、たとえば紙が違うと色が変わってくるのはどうしてでしょうか。紙の色が違うのであれば色の違いも納得できますが、実は白色度が同じ紙であっても色は違ってくるのです。
異なる紙に印刷した場合に色が違ってくるのは、紙によって「ドットゲイン」が異なるからです。また、印刷機や印刷会社によって色が変わるのは、ドットゲインや「ベタ濃度」が違うからです。今回は、印刷の色を左右する最大の要素であるこの二つについて見ていきましょう。
ベタ濃度とは
ベタ濃度とは、インクがベタ(100%)に印刷された状態の色の濃度を意味します。100%ならベタ濃度は100%だろうと思われるかもしれませんが、ここで言う濃度は、分光光度計などで測定される絶対的な濃度のことを指します。
インクが紙の内部に浸透して定着するインクジェット・プリンタなどと異なり、オフセット印刷では、インクが刷版からブランケット、ブランケットから紙へと転写を繰り返しながら紙の表面に盛り上がる形で付着します。その際、インクを印刷機に流し込む量などによって紙の表面に盛られたインクの厚み(インク膜厚)が変わってきます。
カラーインクは、それぞれ特定の波長の光を吸収し、残りの波長の光を反射することで色を表現します。この場合、光を吸収する度合いが高ければ高いほど反射する光は少なくなり、色が濃くなります。光を吸収する度合いはインク膜厚に比例するので、インク膜厚が色の濃さを直接左右することになるわけです。
絵柄によって必要なインク量が違うため、印刷機のオペレーターは印刷前に印刷機でインクを流し込む量を調整するという作業をします。色の濃い面積が多い部分はインクを多めに、色が薄い部分はインクを少なめに流し込まなければならないのです。
この調整作業で、本来必要な量よりインク流量を多めにすればインク膜厚が厚くなり、ベタ濃度は高くなります。つまり、オペレーターのさじ加減一つで、ベタ濃度は簡単に変わってくるのです。ベタ濃度が高くなればそれだけコントラストを強く再現できるため、かつては「インクはできるだけ盛れ」などと言う人もいましたが、もちろん品質的に適正なベタ濃度というものがあるので一概にインクを盛ればいいというものではありません。
なお、デジタル管理システムが普及した現在では、ベタ濃度を数値管理し、印刷品質の安定化を図るというのが一般的になっています。今や日本の印刷物のスタンダードとなりつつあるJapan Colorでも目標値が定められており、その数値を基準にベタ濃度を管理・運用することが求められているのです。
ベタ濃度は、印刷現場において印刷物の色を管理するためのものであり、発注側が知らなくても困るわけではなく、DTPで制作する側が気にしなくても問題はありません。ただし、実際の印刷物の品質に大きく関わる要素であり、ベタ濃度をきちんと管理できている現場は安定した印刷再現が期待できるなど、印刷会社を選定する際の目安と考えることができます。
ドットゲインとは
ベタ濃度は100%ベタの部分の色を測定したものですが、ドットゲインは中間調でデータ上の色と実際に印刷された色に差が生じる現象のことです。
たとえばPhotoshopやIllustratorでシアン50%のオブジェクトを作ったとします。50%ですからそのまま出力された網点をみれば網点と余白の面積は同じになります。ところが、出来上がった刷版を印刷機に掛けて印刷し、色を測定してみると、50%ではなくもっと濃度が高くなるのです。
本来あるべき濃度(データ上の濃度)と実際の濃度が違ってしまうこの現象を「ドットゲイン」と言います。ドットゲインはオフセット印刷では避けられない現象であり、印刷物の色をコントロールする際も、この現象を前提に考えなければなりません。
ドットゲインが起きる原因は大きく分けて二つあります。一つは物理的に網点が大きくなるというもの。フィルム→刷版の焼き付け時や、印刷機でインクを転写し、圧胴で圧力を掛ける際など、網点が本来の大きさよりも大きくなってしまうことがあります。実際の網点そのものが大きくなることで濃度が上がってしまうこの現象を物理的ドットゲインと呼びます(メカニカルドットゲインとも言う)。
もう一つは、網点の大きさではなく、反射する光の量が少なくなることで実質的に濃度が上がってしまう光学的ドットゲインと呼ばれる現象です。印刷物の色は、インクを透過し、紙の表面で反射した光が眼に入ることで感知されます。インクで光が吸収されれば濃度が高くなるというのは先ほど述べましたが、インクの吸収率そのものは同じでも、インクを透過せずに紙で反射するだけだった光(つまり白い部分で反射していた光)がインクを透過するようになれば、濃度は高くなります。
光が紙で反射する仕組みを調べてみると、光は紙の内部に入り込み、紙の繊維によって屈折・乱反射しながら最終的に紙の外に出て行くという複雑な経路を辿ることが分かります。この過程で、インクドット(網点)周辺に照射された光が紙の内部で乱反射し、近くのインク層にぶつかって吸収されるという現象が起きることで紙の外に出る光が減少します。つまり、光の吸収割合が本来の網点面積比よりも多くなり、それによって、結果として濃度が上がってしまうのです。
光学的ドットゲインは物理的ドットゲインよりも大きいというデータもあり、光学的ドットゲインが中間調の色を決める重要な要素であると言えます。
光学的ドットゲインは、紙表面の状態に大きく左右されます。紙の表面が平滑であればあるほどドットゲインは小さく、凹凸が激しければドットゲインも大きくなります。新聞紙のドットゲインが大きいのは紙質に原因があるのです。コート紙と上質紙であれば、コーティングされて表面が平坦なコート紙のほうがドットゲインは小さくなります。
また、スクリーン線数もドットゲインに影響を与えます。網点の周囲長とドットゲインは相関関係にあるため、網点のサイズが小さく密度が高いほど、周囲長(の合計)が大きく、ドットゲインも大きくなります。FMスクリーニングや印刷線数が高い印刷物ほどドットゲインが大きくなるのはそのせいです。
印刷条件と品質の関係を理解するためには、ドットゲインを理解しなければなりません。ドットゲインが大きすぎると安定させるのが厳しく、色のコントロールが難しくなります。たとえば新聞のように紙質が悪い印刷物は、線数を低めにしなければドットゲインが高くなりすぎてきちんと印刷できません。逆に、線数の高い印刷物を作りたければ、紙質を通常の印刷物以上に注意して選ばなければならないということも分かるでしょう。
ドットゲインの影響はDTP作業においても小さくありません。InDesignやIllustratorでオブジェクトの色を指定する際や、デジタルカメラの撮影画像をPhotoshopでCMYKに変換する際、印刷時におけるドットゲインを知らなければ実際の色を想定することができず、色にシビアな仕事だとトラブルになりかねないでしょう。もちろん、そういった知識がなくても作業できるようにAdobe社はJapan Color準拠のICCプロファイルを用意し、自社アプリケーションのデフォルト設定にしているわけです。そのおかげで、モニタの色と印刷物の色がまったく違ったという事態は避けられていますが、厳密なカラー管理が必要な仕事になると、適切なドットゲインに基づくプロファイルかどうかきちんと確認することがより大切になってきます。
ドットゲインやベタ濃度は印刷物の色を決定する重要な要素であり、色分解やカラーマネージメントを理解する上でもその性質や働きについてきちんと知っておく必要があります。
(田村 2006.6.12)
(田村 2025.4.14)